46期 地域文化学科 学習内容(選択科目)へようこそ
| 授 業 日〔場所〕 | テ ー マ | 概 要 | ||
| 2024/10/8(火) 介護研修室 |
農書について学ぶ 近江の農書について学ぶ |
・民俗学とはどのようなものか、また、日本一である滋賀の民俗学の状況について話された後、農作物の栽培法等を記した江戸期の農学者である宮崎安貞著「農業全書」、大蔵永常著「広益国産考」、児島如水・徳重著「農稼業事」等について紹介していただきました。 ・特に「農稼業事」を著わした児島如水と孫の徳重は、近江の出身であり、稲の掛干しの仕方などが記されていることなどを教えていただきました。 |
||
| 2024/10/22(火) 彦根キャンパス |
江戸期の農書を読む | ・大蔵永常著「広益国産考」から砂糖(和三盆)や干し柿の作り方などについて解説されました。また、カラスウリの根から「おしろい」がつくられることや右縄と左縄の違いなどについても教えていただきました。 | ||
| 2024/11/12(火) 伊吹山文化資料館 |
【校外学習】 民俗資料収集の方法(1) 「伊吹山文化資料館」見学 |
・粕渕先生が収集された火打石を受講生に回して火打ち体験をするなど、昔の人が使った火きり具や除雪具などについて学び、追体験を行う実験的民俗学の重要性について説かれました。 ・伊吹山文化資料館を見学し、伊吹山の自然や歴史、養蚕やもぐさなど伊吹山の恵みとなりわい、昔の人々の暮らしなどについて粕渕先生が展示物の解説をしてくださいました。 |
||
| 伊吹山文化資料館 | ||||
| ※ 上の写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 ※ また、右のボタンを押すと「校外学習等写真集」を見ることができます。 |
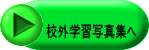 |
|||
| 2024/11/26(火) 彦根東高等学校 多目的ホール |
【校外学習】 民俗資料収集の方法(2) 「製茶図解」を読む 「御座所(大正天皇宿泊施設)」等見学 |
・粕渕先生の案内・解説で、彦根東高等学校敷地内にある大正天皇御座所(宿泊施設)、銀杏の精子を発見した平瀬作五郎を讃える大銀杏などを見学しました。 ・粕渕先生が収集された升(ます)、斗掻(とかき)、道中着(合羽)、引札(カレンダー)などの現物を見せながら使い方などを説明されました。 ・彦根藩より明治4年に出版された「蚕桑図解」、「製茶図解」について説明され、近江で行われた茶の栽培から茶摘み、製茶に至る過程等について学びました。 |
||
| ②大銀杏 | ③道中着の着方を教える粕渕先生 |
|||
| ※ 上の写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 ※ また、右のボタンを押すと「校外学習等写真集」を見ることができます。 |
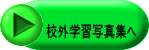 |
|||
| 2024/12/3(火) 介護研修室 |
学習のまとめ |
・粕渕先生が収集された古い絵はがきから昔の風俗を学ぶとともに、黒色火薬の作り方、ネズミ捕り器などの昔の小道具について説明がありました。 | ||
| ①粕渕先生授業風景 | ②粕渕先生を囲んで | |||
| ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 | ||||
| 2024/12/17(火) 滋賀大学経済学部附属資料館 |
【自主学習】 「滋賀大学経済学部附属資料館」見学 |
・11月26日午後に予定していた滋賀大学経済学部附属資料館見学が中止となったため、学生有志で見学会を実施しました。 | ||
| 授 業 日〔場所〕 | テ ー マ | 概 要 | ||
| 2024/12/10(火) 介護研修室 |
湖東焼の盛衰と美 彦根城を世界遺産に |
・彦根藩井伊家が庇護した湖東焼の特徴、制作工程、経営の推移等を学んだ後、壺などの湖東焼作品をスライドで鑑賞しました。 ・彦根城の世界遺産登録に向けたコンセプト等について学んだ後、天守や櫓、石垣などについてスライドで説明がありました。 |
||
| 2024/12/24(火) 荒神山自然の家 |
【校外学習】 荒神山古墳とその時代 |
・前方後円墳など古墳の形式や荒神山古墳の特徴などを学んだ後、小雨がぱらつく中荒神山古墳に赴き、谷口先生から後円部や前方部の形状等の説明を聞きました。 | ||
| ①谷口先授業風景 | ②荒神山古墳 | |||

|
 |
|||
| ※ 上の写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 ※ また、右のボタンを押すと「校外学習等写真集」を見ることができます。 |
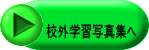 |
|||
| 2025/1/7(火) 柏原宿歴史館 |
【校外学習】 街道と宿場 |
・江戸時代の五街道や宿場(問屋、本陣・脇本陣、旅籠屋)の概要のほか、高札場など街道の施設について説明がありました。 ・柏原宿歴史館内の福助人形や伊吹もぐさなどの展示を見学後、中山道柏原宿を散策しながら谷口先生から本陣跡や常夜灯・高札場跡などについて解説していただきました。 |
||
| ①柏原宿歴史館 | ②中山道柏原宿にて | ③JR柏原駅にて伊吹山をバックに | ||
| ※ 上の写真をクリックすると拡大画像を見ることができます ※ また、右のボタンを押すと「校外学習等写真集」を見ることができます。 |
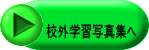 |
|||
このページのトップに戻る
■ 分野:近江と文学 講師:旅行作家 西本 梛枝 氏
| 授 業 日〔場所〕 | テ ー マ | 概 要 | ||||
| 2025/3/4(火) 介護研修室 |
近江の文学的風土 近江が登場する文学作品 |
・講義の目的は、近江が登場する文学作品を素材に、近江の風土を知り、近江の良さに気づき、併せて本の楽しさに触れることであると述べられた後、3~5月全9回の講義の内容を紹介されました。 ・また、「水の国」・「道の国」である近江の湖北・湖東・湖南・甲賀・湖西のエリア毎に特色ある風土について説明されました。 ・午後は、近江ゆかりの主な文学作品の概要、考察を紹介されました。これらの作品を通して、近江の見慣れた風景を新鮮な風景に見直すきっかけになることが期待されます。 |
||||
| 西本先生授業風景 | 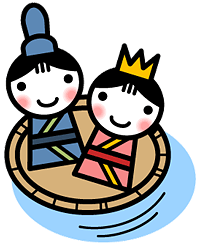 |
|||||
| ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 | ||||||
| 2025/3/11(火) 介護研修室 |
城山三郎 『一歩の距離』 獅子文六 『但馬太郎治伝』 |
・城山三郎著「一歩の距離 小説 予科練」について、あらすじ、時代背景、滋賀との関わり、城山三郎のプロフィールと思いなどを西本先生に教えていただきました。昭和19年から終戦までの大津海軍航空隊(大津市際川。現陸上自衛隊大津駐屯地)、滋賀航空隊(大津市唐崎)を舞台に、飛行予科練の少年達が下士官達のいじめに耐えながら特攻として死ぬ「一歩」を踏み出すことの苦悩を描き、「”国家の嘘を”を書くために作家になった」という城山の思いがこもる作品であることを知りました。 ・獅子文六著「但馬太郎治伝」については、実在した人物の実際にあった話であることを強調された上で、登場人物やあらすじなどについて説明されました。作品中の「但馬太郎治」は、現犬上郡豊郷町出身の豪商薩摩治兵衛の孫薩摩治郎八であり、「バロン(男爵)サツマ」「東洋の貴公子」と呼ばれ、パリで優雅な生活を送り、芸術家を支援するとともに、寄付によりパリ国際大学都市日本館を建設し、現在でも日本人留学生の宿舎や文化活動の会場として活用されていることを教えていただきました。また、併せて八幡商人や日野商人などの近江商人の特徴や理念についても学びました。 |
||||
| 2025/3/25(火) 犬上郡豊郷町 |
【校外学習】 但馬太郎治こと薩摩治郎八ゆかりの地豊郷を歩く |
・西本先生に案内・解説していただきながら、犬上郡豊郷町の「先人を偲ぶ館」、「薩摩治兵衛記念館」、「豊郷小学校旧校舎群」、「伊藤忠兵衛記念館」を訪ねました。 ・「先人を偲ぶ館」では、豊郷病院を設立した伊藤長兵衛、豊郷小学校の建設に寄与した古川鉄治郎、一代で巨万の富を築き「木綿王」と呼ばれた薩摩治兵衛、その孫でバロン(男爵)サツマと呼ばれた薩摩治郎八、伊藤忠・丸紅の創始者伊藤忠兵衛など豊郷が育んだ郷土の先人達の活躍について遺品などの展示物や説明パネルを見ながら学びました。 ・「薩摩治兵衛記念館」は、明治20年に新築された旧豊郷尋常高等小学校本館で、初代・2代薩摩治兵衛、そして、獅子文六著「但馬太郎治伝」の太郎治のモデルとなった薩摩治郎八の活躍を記したパネルや写真が展示されていました。 ・「豊郷小学校旧校舎」は丸紅の専務古川鉄治郎が私財の2/3を寄贈し、ウィリアム・メレル・ヴォーリズの設計により建設され、「白亜の教育殿堂」「東洋一の小学校」として町民に愛されてきました。最近は、アニメ「けいおん!」の主人公らが通う高校のモデルとなったといわれ、聖地巡礼に多くのファンが訪れています。 ・「伊藤忠兵衛記念館」は、伊藤忠・丸紅の創始者伊藤忠兵衛の旧邸、二代忠兵衛の生家に彼らの愛用の品などが展示され、初代忠兵衛と八重夫人の当時の暮らしぶりや近江商人の精神について記念館のガイドの方から学びました。 |
||||
| ①先人を偲ぶ館 | ②薩摩治兵衛記念館 | |||||
| ③豊郷小学校旧校舎/階段手すり(うさぎとかめの真鍮像) | ④伊藤忠兵衛記念館 | |||||
|
||||||
| ※ 上の写真をクリックすると拡大画像を見ることができます ※ また、右のボタンを押すと「校外学習等写真集」を見ることができます。 |
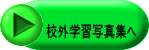 |
|||||
| 2025/4/8(火) 介護研修室 |
童門冬二 『小説中江藤樹』 永井路子 『雲と風と』 |
・童門冬二著「小説 中江藤樹」について、西本先生が著者竜門冬二の歴史観を述べられた後、安曇川生まれの近江聖人と呼ばれた中江藤樹が生まれてどのように学問にかかわっていったのか、また、「致良知」の領域まで極めていったのかを学びました。さらに、藤樹が10歳から27歳まで過ごした伊予大洲(現愛媛県大洲市)について、観光地図をもとに、大洲城や中江藤樹邸など小説に登場する舞台について詳しく説明してくださいました。 ・午後は、まず、歴史的事実と歴史的事実を線で結んで、それに資料とそれを読む作者の想像で肉付けをして歴史小説が生まれると西本先生は力説された上で、永井路子著「雲と風と」は、求道の道を巡り苦悩する最澄と、新しい世の中を作ろうと苦悩する桓武天皇という、同時代を生きた二人を並べ、最澄の人生に迫っていく作品であると説明されました。「我がために仏をつくることなかれ。我がために経を写すことなかれ。我が志を述べよ。」という最澄が亡くなる前に弟子達に言った最後の言葉が、「最澄の真面目な性格をあらわしている」と西本先生が述べられたことが印象的でした。 |
||||
| 2025/4/22(火) 高島市 |
【校外学習】 中江藤樹のふるさと高島市安曇川と高島を訪ねる |
・午前中は、地元の観光ガイドさんの案内により高島市旧高島町内を巡りました。万葉の時代に「香取の海」と呼ばれる入り江だった「乙女ヶ池」、明智光秀の縄張りによって築城され、織田信澄(信長の甥)が初代城主だった「大溝城跡」、江戸時代に大溝藩主分部(わけべ)氏によって整備された「大溝陣屋」の「総門」、城下町の町割りの整備によってつくられた飲用・防火用の生活用水路である「町割り水路」などを見学しました。 ・午後は、高島市旧安曇川町に移動しました。講師の西本梛枝先生の案内により、王陽明の生地中国浙江省余姚市との友好交流を記念して建設された中国式庭園「陽明園」、近江聖人といわれた陽明学の祖、中江藤樹を敬慕する人々の協力により建てられた「藤樹神社」、「中江藤樹墓所」がある「玉林寺」を巡りました。その後、中江藤樹の住居・講堂跡である「藤樹書院」において、「藤樹書院」の上田藤市郎先生から「藤樹書院」のあゆみ、藤樹の人柄、教えについて学びました。上田先生は、「愛敬」「到良知」「五事を正す」など藤樹が説いた理念をユーモアを交えわかりやすく説明されるとともに、地元の小学3年生が将来の夢を作文に書いて「藤樹書院」に奉納し、それを成人式に受け取る行事が続いていることなど、藤樹の教えが地域の人々に愛され、根付いていることを教えていただきました。 |
||||
| ①大溝城跡(天守台跡) | ②大溝陣屋 総門 | ③陽明園(陽明門) | ||||
|
||||||
| ④中江藤樹墓所(玉林寺) | ⑤藤樹書院(1) | ⑥藤樹書院(2) | ||||
|
||||||
| ※ 上の写真をクリックすると拡大画像を見ることができます ※ また、右のボタンを押すと「校外学習等写真集」を見ることができます。 |
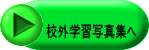 |
|||||
| 2025/5/13(火) 介護研修室 |
学習のまとめ 発表会 |
・滋賀の文学について思い思いのテーマを選び、一人づつ研究したことを発表しました。 ・発表内容は、滋賀にゆかりのある人の小説、滋賀での歴史的な出来事を題材にしたもの、俳人芭蕉を取り上げたもの等々多岐に渡っていました。 ・発表形式も、白板に写真を貼ったり、パソコンのプレゼンソフトを使ったり、原稿の読み上げも朗読調だったりと個性が発揮されていました。 ・その地を実際に歩き研究したものが多かったので重厚な内容になっていました。 ・全員が滋賀に対する熱い思いを込めて語り、聴きごたえのある発表会でした。 |
||||
| ①西本先生を囲んで | ②感謝の色紙贈呈 | ③色紙 | ||||
| ※ 上の写真をクリックすると拡大画像を見ることができます ※ また、右のボタンを押すと「校外学習等写真集」を見ることができます。 |
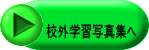 |
|||||
■ 分野:明智光秀と坂本城・坂本の史跡を訪ねる 講師:滋賀県文化スポーツ部文化財保護課職員
| 授 業 日〔場所〕 | テ ー マ | 概 要 | |||
| 2025/5/20(火) 介護研修室 |
明智光秀と坂本城 講師: 県文化財保護課 松下 浩 氏 井上 優 氏 |
近江になじみの深い戦国武将の明智光秀と、いまだに謎の多い坂本城の話でたいへん興味深い内容でした。 ・午前は、坂本城と明智光秀に関する丁寧な調査と深い洞察に裏打ちされた松下浩先生の研究成果が紹介されました。坂本城の遺跡や出土遺跡のスライドを通して、戦国時代の近江の姿が学術的に明らかにされました。 ・午後は、明智光秀と坂本城にまつわる伝承を含め、ロマン溢れる話を井上優先生が紹介されました。明智家菩提寺としての西教寺、光秀の愛妻熙子を含めた明智一族の墓、源信が起こした聖衆来迎寺と西教寺との関わり等が紹介されました。 また、明智光秀が実は近江出身だった等、生誕地の諸説がたいへん面白かったです。 |
|||
| 2025/6/10(火) 坂本地域(西教寺・日吉大社) |
【校外学習】 坂本の史跡を訪ねる 講師: 県文化財保護課 長谷川 聡子 氏 福吉 直樹 氏 |
・午前は、滋賀県文化スポーツ部文化財保護課の長谷川聡子先生の案内により西教寺(大津市坂本五丁目)を見学しました。長谷川先生から、西教寺の縁起や明智光秀との関わりなどの概要を説明いただいたあと、重要文化財(以下、「重文」)である本堂および客殿それぞれの建物の構造、屋根や柱、欄間、装飾などの建造物の特徴を中心に詳しく解説していただきました。 ・午後は、同文化財保護課の福吉直樹先生の案内により日吉大社(大津市坂本五丁目)を見学しました。長谷川先生からは、雨が強まる中、西本宮の楼門(重文)、拝殿(重文)および本殿(国宝)ならびに東本宮の楼門(重文)、拝殿(重文)および本殿(国宝)などの建造物の構造、屋根や柱等の特徴について詳しく解説していただきました。また、最後に大宮川に架かる二宮橋、走井橋、大宮橋の日吉三橋(重文)と日吉大社独特の山王鳥居について説明いただきました。 |
|||
| ①西教寺本堂 | ②西教寺客殿 | ③明智光秀公と一族の墓 | |||
| ④日吉大社西本宮楼門前にて | ⑤日吉大社東本宮本殿 | ⑥日吉三橋のうち二宮橋 | |||
| ※ 上の写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 ※ また、右のボタンを押すと「校外学習等写真集」を見ることができます。 |
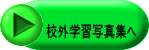 |
||||
■ 分野:織田信長と近江の武将、そしてその末裔たち 講師:元東近江市史編纂室長 山本 一博 氏
| 授 業 日〔場所〕 | テ ー マ | 概 要 | ||||||
| 2025/6/24(火) 介護実習室 |
織田信長と近江の武将、そしてその末裔たち(1) ~当国一乱 信長以前の近江~ ~用意周到 義昭の上洛~ |
・午前は、講師の山本一博元東近江市史編纂室長が、このカリキュラムや校外学習のねらいのなどをまず最初に語られました。特に、「皆さん一人一人が当時の近江の戦国武将の一人となり、自分ならどんな選択をするのか想像してください」、「講義の中で紹介する出来事、武将の行動などから特に興味のあることを見出し、自分なりに調査学習を」、「歴史事項を遠い昔のことととらえるのではなく、親近感を持って感じていただきたい」と強調され、私たち学生の探究心を鼓舞されました。 ・その後、近江守護佐々木氏の出自、六角など佐々木四家、観音寺騒動、六角式目など当国一乱状態の信長以前の近江の状況についてわかりやすく詳しく教えていただきました。 ・午後は、足利義昭の15代将軍即位の経緯と当時の情勢、義昭上洛に向け織田信長が敵を排除し、また調略などにより味方につけ、岐阜から京への通路を用意周到に確保していった経緯について詳しく説明されました。特に、観音寺城落城六角逃亡に至る箕作山城の攻防では、東山御文庫所蔵文書「足利義昭入洛記」を引用され、「信長公記」の記述ほど箕作山城たやすく落城せず、六角勢もある程度抵抗していたと強調されました。 |
||||||
| 山本先生授業風景 | ||||||||
| ※ 写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 | ||||||||
| 2025/7/1(火) 永源寺コミュニティセンター 東近江市永源寺地区 |
【校外学習】 織田信長と近江の武将、そしてその末裔たち(2) ~危機一髪 信長の千草越~ 市原の城・千草街道 |
・午前は、永源寺コミュニティセンターにおいて講師の山本一博先生が、「危機一髪 信長の千草越」と題して、信長の朝倉攻め、浅井長政の謀反などの情勢を述べられた後、浅井勢が鯰江城へ人数を入れ、市原の郷に一揆を催したため、信長が千草越にて岐阜へ戻る途中、杉谷善住坊が千草山中において信長に鉄砲を打ち、信長の身体をかすったが無事だったことなどを説明されました。 ・また、市原野城跡には遺構が残っていないが、白鳥社城跡には土塁が残っており、両者の間に溝を巡らす程度の郭が拡がっていたと推測されるという「永源寺町史」の記述を紹介されました。 ・午後は、まず、信長も利用した鈴鹿越えの街道である、八風街道と千草街道の分岐点(東近江市永源寺町如来)を山本先生の案内で見学しました。その後、白鳥神社(東近江市市原野町)に向かい、この地域のことに詳しい中寺さんに案内していただき、白鳥社城の土塁跡などについて詳しく解説していただきました。 ・そして、山本先生の案内で、信長が千草越の際休息をとった速水家にある「信長駒繋ぎの松」(東近江市甲津畑)、小倉右京亮の所領であった「高野館遺跡」(東近江市永源寺高野町)と信長の側室であったお鍋の方の屋敷跡(同)を見学しました。 |
||||||
| ①山本先生授業風景 | ②八風街道・千草街道分岐点 | ③白鳥神社(1) | ||||||
| ④白鳥神社(2)土塁跡 | ⑤白鳥神社(3) | ⑥信長駒繋ぎの松 | ⑦高野館跡・お鍋の方屋敷跡 | |||||
| ※ 上の写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 ※ また、右のボタンを押すと「校外学習等写真集」を見ることができます。 |
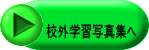 |
|||||||
| 2025/7/15(火) 能登川コミュニティセンター 東近江市能登川地区 |
【校外学習】 織田信長と近江の武将、そしてその末裔たち(3) ~有言実行 比叡山の焼討~ 志村城址・川原崎助右衛門顕彰碑 |
・午前は、能登川コミュニティセンターにおいて講師の山本一博先生が、「有言実行 比叡山の焼討」と題して、まず、元亀元年(1570年)の元亀争乱のうち、近江での滋賀(志賀)の陣や比叡山焼き討ちについて説明されました。 ・特に、午後から見学する予定の志村城(址)のことや、伊庭の川原崎助右衛門のことなど能登川地域に関わることについて詳しく教えていただきました。 ・午後は、まず、東近江市新宮町に向かい志村城址周辺を見学しました。志村城は、志村氏(新村氏)の代々の居城で、元亀2年(1571年)信長勢の佐久間重盛らが攻撃し、首670人を討ち取ったところです。志村城址の外堀であった「さかさ川」、「殿様の墓」、多量に掘り出された石仏が集められた墓地などを山本先生に案内いただき詳しく説明していただきました。 ・次に、伊庭集落に移動し、連歌で有名な伊庭出身の宗祇の歌碑、明治29年(1896年)の洪水水位の石碑、伊庭城石垣跡を山本先生に案内していただき、正厳寺に向かいました。 ・正厳寺本堂では住職から、お寺の歴史、川崎助右衛門の功績とそれを讃える境内にある「愛郷流水の碑」のことを詳しく教えていただくとともに、本堂にある「光明本尊」という掛軸の複製を間近で見せていただきました。 ・その後、山本先生の案内で、天正7年(1579年)の安土宗論における浄土宗側の論者貞安が住職だった「妙金剛寺」や葦葺きが特徴的な「仁王堂」がある「大濱神社」などを見学し詳しく説明いただきました。 |
||||||
| ①山本先生授業風景 | ②さかさ川 | ③殿様の墓 | ④出土した多数の石仏 | |||||
|
||||||||
| ⑤宗祇歌碑前にて | ⑥正厳寺本堂にて | ⑦光明本尊 | ⑧大濱神社 仁王堂 | |||||
| ※ 上の写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 ※ また、右のボタンを押すと「校外学習等写真集」を見ることができます。 |
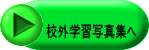 |
|||||||
| 2025/8/5(火) 愛東コミュニティセンター 東近江市愛東地区 |
【校外学習】 織田信長と近江の武将、そしてその末裔たち(4) ~盛者必衰 六角の没落~ 鯰江の城・井元城 |
・午前は、愛東コミュニティセンターにおいて講師の山本一博先生が、「盛者必衰 六角の没落」と題して、まず、午後に訪れる「鯰江の城」について説明された後、鯰江の城落城後の六角承禎の足跡、足利義昭に従った承禎の長子義堯(義治)、断絶したとされていた六角氏の末裔が明治まで加賀藩士として存続していたことが平成末期に判明したこと、義昭の帰洛願望と本能寺の変後に秀吉の承諾により帰洛できたことなどを教えていただきました。 ・特に、二重角馬出しを持つ井元城は従来から信長軍の付城とされてきたが、森村城と中戸城とこの井元城を合わせたものが信長公記に出てくる「鯰江の城」ではないかという見解もあることを詳しく説明していただきました。 ・午後は、井元城址、中戸址、鯰江城(森村城)址を順次巡り、愛知川の河岸段丘を巧みに利用した土塁、堀跡などを山本先生の案内・解説により見学しました。 |
||||||
| ①井元城址 二重角馬出し | ②中戸城址 土塁跡 | ③鯰江城址付近 | ④鯰江城址土塁跡 | |||||
| ⑤殿さん墓(専修院境内) | ⑥鯰江城址 土塁跡 | ⑦鯰江城址 石碑 | ⑧鯰江城址 土塁跡 | |||||
| ※ 上の写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 ※ また、右のボタンを押すと「校外学習等写真集」を見ることができます。 |
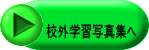 |
|||||||
| 2025/9/2(火) 近江商人ふるさと館 蒲生郡日野町 |
【校外学習】 織田信長と近江の武将、そしてその末裔たち(5) ~千差万別 近江衆の行末~ 中野城・信楽院 |
・午前は、近江日野商人ふるさと館「旧山中正吉邸」において講師の山本一博先生から、「千差万別 近江衆の行末」と題して、大津城の戦いなど京極氏のその後、茶々・初・江の浅井三姉妹など浅井氏にかかわるその後のこと、そして、六角氏の重臣であった蒲生氏について説明していただきました。 ・特に、二代将軍となる徳川秀次に嫁いで三代将軍となる家光など2男5女に恵まれたこと、そのうち茶々に養育された、定子が関白九条家に嫁ぎ、九条家の家系が、大正天皇の皇后貞明皇后につながり、昭和天皇以降の現在の天皇家に浅井の血が流れていることなどを学びました。 ・また、信長の娘冬姫と蒲生氏郷が結婚した縁から、本能寺の変後氏郷の父賢秀が信長の妻子を日野城に避難させたこと、氏郷が松坂12万石、会津42万石から92万石へと出世していったことなどを詳しく説明していただきました。 ・その後、近江日野商人ふるさと館の職員さんに「旧山中正吉邸」内を案内・説明いただきました。 ・午後は、まず、氏郷が生まれ育った中野城跡を訪れ、山本先生の案内・解説で土塁跡、堀跡などを見学した後、蒲生賢秀公の墓がある法雲寺の住職から賢秀や氏郷のことなどについて熱のこもった説明を受けました。 ・その後、山本先生の案内で蒲生氏郷公遺髪塔がある信楽院(しんぎょういん)、ひばり野公園にある蒲生氏郷公像を見学しました。 |
||||||
| ①山本先生授業風景 | ②近江日野商人ふるさと館 | ③中野城跡 | ④中野城跡 | |||||
| ⑤法雲院本堂前にて | ⑥蒲生賢秀公墓 ・一橋利政公之墓 |
⑦蒲生氏郷公遺髪塔 | ⑧蒲生氏郷公像 | |||||
| ※ 上の写真をクリックすると拡大画像を見ることができます。 ※ また、右のボタンを押すと「校外学習等写真集」を見ることができます。 |
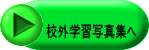 |
|||||||
| 2025/9/16(火) 介護研修室 |
織田信長と近江の武将、そしてその末裔たち(6) 個人発表 |
・講師の山本一博先生からこれまで学んだことをもとに、学生それぞれがテーマを決めて、発表を行いました。 ・取り上げたテーマは、織田信長、片桐且元、京極高次、山内一豊、朽木元綱、足利義昭、明智光秀、佐々木六角氏一族、お鍋の方などの人物、安土城、観音寺城などの城郭のほか、本能寺、十二坊、元亀争乱、近江一向一揆、楽市楽座、近江の道など学生の関心に応じて様々でした。 ※ 右のボタンを押すと発表風景の写真を見ることができます。 |
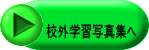 |
|||||