| 2021年10月8日(水) | 終日 |
  |
仰木の里 棚田の水環境システム |
| 成安造形大学 近江学研究所 穴風 光恵先生 大原 歩先生 | |
| 午前 成安造形大学内で木原先生と穴風先生の講義を受けた。 午後 車で仰木の里を案内していただいた。 |
|
| (文責) 鯉タロー |
| 2021年10月13日(水) | 午前 |
 |
「環境まちづくり活動」の企画と運営について① |
| 水色舎 滋賀県立大学非常勤講師 佐々木 和之先生 | |
| 午後 | |
| 食品ロスを減らすために | |
| 消費生活アドバイザー 鈴木 光子先生 | |
| 2021年10月20日(水) | 終日 |
.jpg) |
湖南アルプス自然休養林での植物観察 |
| 龍谷大学教授 宮浦 富保先生 | |
| 先生を先頭に一丈野駐車場を出発して、北谷林道からたまみづきの道に入り、落ヶ滝を目指した。歩きながら、この一帯がはげ山になり再生するまでの歴史や花崗岩でできていることと植生への影響の説明を受けた。 平坦な誰でも楽しめる道が整備されていたが、滝への道はところどころ急登であった。その間、ドングリを拾ったり、土留めの石垣を観察したりなどした。滝から引き返して桐生キャンプ場で昼食をとった。午後からはサブ谷林道から南谷林道に入り、逆さ観音、オランダ 堤を経て、駐車場まで戻った。 先生のご専門は樹木ということで、数多くの樹木の説明を聞き、葉を触り、匂いをかぎ、味をみるという五感を使った観察会となった。 伊吹山では草花を学んだが、今回は樹木中心に学べたのが良かった。五感を使って植物に迫った事に、新鮮さを感じた。 クラスの皆が声をかけながら山道を歩き、達成感・連帯感がえられた。 滝への道はやや険しく、軽登山靴を履き、ポールを持っていくのが良いかもしれないと感じた |
|
| (文責) タカちゃん |
| 2021年11月24日(水) | 午前 |
 |
特色ある滋賀の内水面漁業・養殖業の活性化をめざして ~魚の採卵受精実験~ |
| 滋賀県醒ヶ井養鱒場 場長 桑村 邦彦先生 | |
| 後輩の43期生と合同で受講した。 ニジマスの採卵と受精実験をおこなった。 各自受精卵を持ち帰ったが1ヶ月後のふ化は如何に??! |
|
| 午後 | |
.jpg) |
「居醒の清水」を水源とする地蔵川での淡水魚「ハリヨ」と 淡水植物「梅花藻」の観察 |
| 元滋賀県立虎姫高校教諭 村居 利美先生 | |
午後は村居先生の案内で地蔵川周辺の散策をし 梅花藻、絶滅危惧種のハリヨや天然記念物のオハツキイチョウなど説明をいただいた。 |
|
| 2021年12月15日(水) | 午前 |
   |
湖北の野鳥観察 |
| 湖北野鳥センター 職員 植田先生 | |
| 湖北野鳥センターを訪れた。 この時期多くの渡り鳥が飛来して湖面を賑わしている。 中でも「山本山のおばあちゃん」と呼ばれるオオワシ、ハクチョウやオオヒシクイが観察できた。 大半が人口の湖岸堤で囲われた琵琶湖の中で、原風景が残る貴重な場所である。 大切に未来に残したい風景と生態系である。 |
|
| (文責) 鯉タロー | |
| 午後 | |
⇩西野水道 .jpg)  .jpg) ☜田川カルバート ☜田川カルバート |
北の水環境(治水について) |
| 元滋賀県立虎姫高校教諭 村居 利美先生 | |
午後は江戸時代に行われた2ケ所の治水工事について現地を訪れ学んだ。 1)西野水道 余呉湖から琵琶湖に流れ込む余呉川流域の治水工事で作られた水道である。 1840年から1845年にかけて行われた硬い岩盤の難工事であったそうだ。その後昭和に入って2代目、3代目の水道(隧道)ができ、3代目が余呉川のトンネルとして琵琶湖に流入している。今回初代の水道(真っ暗で一人が通るのがやっとの細い岩盤のトンネル)を歩いた。 2)田川カルバート 姉川と高時川(妹川)が合流する地点にもう一本、田川が高時川に流れ込んでいた。 高時川が天井川となり田川の流れが悪化し、たびたび氾濫を招いた。左の写真は現在の田川カルバートで人工河川の下流側からの眺めである。このトンネルの上を高時川が流れている。 |
|
| (文責) 鯉タロー |
| 2022年2月2日(水) | 午前 |
 |
ヨシの働き ~びわ湖 美しさと豊かさを永遠に~ |
| 滋賀県地球温暖化防止活動推進員 松田 明子先生・井上 達朗先生 | |
| 午後 | |
 |
琵琶湖の蜃気楼 びわ湖大橋の様々な形をシミュレーションする |
| 琵琶湖地域環境教育研究会 松井 一幸先生 | |
| 松井先生のホームページより (上)びわ湖大橋の蜃気楼 (下)通常の風景 | |
| 2022年2月16日(水) | 午前 |
 |
学習のまとめ 今後に向けて |
| 元滋賀県立虎姫高校教諭 村居 利美先生 | |
| 午後 | |
 |
SDGsカードゲーム・ワークショップ |
| 環境型社会創造研究所えこら 藤田 アニコー先生 | |
| 2022年3月9日(水) | 午前 |
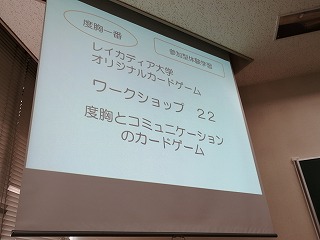 |
環境保全の担い手に向けた学習プログラムについて |
| みどりと水フォーラム代表 温暖化防止推進員 丸山 郁夫先生 | |
| 高島屋時代の経験を元に、「コミュニケーション力」のお話。 ・「コミュニケーション」はしゃべる事よりもまず「人の話を聞く事が大切」 ・環境保全の担い手は、周りの方に広げる用に、「行動する伝道師」 ・挨拶が全て。挨拶はまず自分から(相手に期待しないこと) 【感想】 「度胸」を付けるためのワークショップは楽しかった。 |
|
| (文責) クマさん | |
| 午後 | |
 |
「環境まちづくり活動」の企画と運営について② |
| 水色舎 滋賀県立大学非常勤講師 佐々木 和之先生 | |
| (昨年10月からの継続講義) なぜ「ビジョン(理想像)」が必要か? ビジョンは「より具体的に書く事」:奇麗な水といっても、人により「奇麗」は異なる。 |
|
| (文責) クマさん |