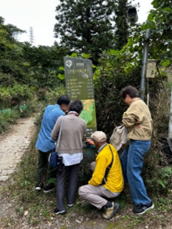課題学習グループ
快童5
テーマ:「街道」から見た、城と古墳(仮称)
【活動目的】
城と古墳は、前者が中世・戦国・近世の軍事的施設、後者が古代の宗教的施設という意味合いを持つ点で違いがあるが、どちらも人々に秩序の存在およびその背後にある権力や権威をイメージさせるシンボル的建造物であった点では共通している。
では、なぜそこに城や古墳が立地するようになったのかと思いをめぐらした場合に、両者の建造目的が最大限に発揮できる場所であることに思い至る。そしてそうした場所とは、多くの人々が頻繁に往来する政治的・経済的に重要なルートすなわち「街道」に沿ったところではないかと考えた。城も古墳もその建造目的から考えて、できるだけ多くの人々に「見てもらってなんぼ」の施設だからである。
近江の場合、古来陸地に限らず琵琶湖やそこに流れ入る多くの河川が「街道」として利用された。特に、鉄道や自動車もなかった前近代では、日本一の面積を誇る琵琶湖の湖上交通を利用でき、しかも都のあった奈良や京都に隣接していた、近江が有する「街道」の重要性は際立っていた。
快童5では、このような認識を前提に、ビジュアル装置としての城・古墳と「街道」の位置関係や、様々なタイプの「街道」のあり方を調査することで、近江の特殊性と重要性を明らかにし、ひいて滋賀の魅力再発見の一助となることを目指している。
【進捗状況】
R 6/10/22(火) 小関越え、琵琶湖疎水第一竪坑、山中越え、逢坂越えの現地調査
大津市で、東海道と北国街道の関所があった付近、及び山中越えを見下ろす位置にあった宇佐山城(古墳)・壺笠山城(古墳)付近を調べた。
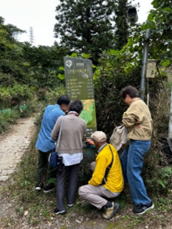
令和6年10月22日
小関越え分岐点の説明板を清掃
R 6/11/1(金) 草津宿、青地城址、小槻神社、部(へ)田(た)古墳群の現地調査
草津市で、東海道と中山道(旧東山道)の分岐点草津追分と、ここに程近い青地城址と部田古墳群を調べた。

令和6年11月1日
草津宿本陣前で
R 6/11/21(木) 番場宿、山津照神社古墳、朝妻湊、中山道と北国街道の現地調査
米原市で、中山道の宿場町と付近の城・古墳、江戸期以前に湖上交通を支えた湊、街道の分岐点を調べた。

令和6年11月21日
中山道番場宿石碑前で

令和6年11月21日
中山道と北陸道分岐点石碑前で
R 6/12/16(月) 熊野本古墳群、清水山城址、田中王塚古墳、鴨稲荷山古墳の現地調査
高島市で、当地の城・古墳と北国街道(西近江路)との位置関係を調べた。

令和6年12月16日
熊野本古墳群を歩く

令和6年12月16日
清水山城主郭より高島平野と琵琶湖を望む
R7/1/14(火) 大石義民碑、浄土寺・大石東館跡、佐久奈度神社、富川磨崖仏(耳垂れ不動)、
小川城跡、紫香楽宮跡の現地調査(紫香楽宮跡は時間の都合で案内看板まで)
街道、関所、城に関わって、支配者としての領主と支配される領民との関係を考えた。

令和7年1月14日(大津市大石関津)
江戸時代初頭、住人を守るために処刑された二人を顕彰する大石義民碑
大石関のあった関津(せきのつ)峠で処刑された

令和7年1月14日(甲賀市信楽町小川)
支配する平地や川を見渡す小川城跡からの眺望
小川城:鎌倉末期(1300年頃)~安土桃山時代(1595年廃城)
R7年2月5日(火) 膳所城跡、膳所神社、禾津頓宮址、茶臼山古墳、園城寺の現地調査
東海道、琵琶湖、瀬田川、瀬田唐橋と城、古墳との関係を考えた。

令和7年2月5日(大津市本丸町)
膳所城跡入口の門(復元)
膳所城の城門は、膳所神社、篠津神社、鞭崎神社などに移築されている。

令和7年2月5日(大津市秋葉台)
茶臼山古墳
琵琶湖、のちの時代の東海道を見下ろすに位置ある
今後の予定
3月:近江八幡市沖島等