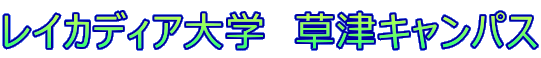
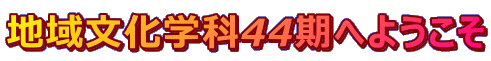
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
民俗学あり、文学あり、城・史跡巡りあり、滋賀の各地で育まれた文化、刻み込まれた歴史などについて学んでいます。
草津キャンパスを中心にして彦根、伊吹山、豊鄕、高島、東近江、甲賀、高月、柏原など文化・歴史の背景となっている滋賀の地を実際に訪問し、
土地それぞれの空気を感じながら学習しています。校外学習終了後、各自の調査結果をまとめ、発表会で報告しています。
このページでは学科員皆さんの選択講座取り組み状況を紹介しています。
なお、史料、写真などが非常に多いため、掲載記事を以下のように分類して紹介します。
中井先生講座は1学年の9月開始でしたが、学年がまたがるため、2学年分の記事に掲載しています。
1.1学年
ご覧になられたいテーマの写真をクリックしてください。↓
| 講座 | 先生 | 主なテーマ、開催時期 |
リンク先 | 発表会、写真集 |
| 選択講座 | 粕渕先生 | 「滋賀の民俗学」 2022年10月~2023年1月 |
 |
 |
| 西本先生 | 「近江の文学的風土」 2023年1月~4月 |
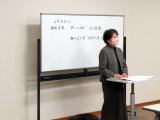 |
 |
|
| 滋賀県文化財 保護課学芸員 |
「明智光秀と坂本城、坂本の史跡」 2023年5月 |
 |
――― | |
| 山本先生 | 「織田信長と近江の武将」 2023年6月~同8月 |
 |
 |
2.2学年